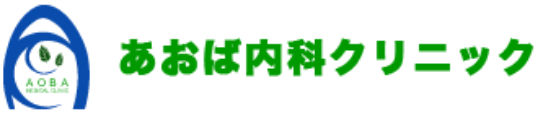Kidney
腎臓病
こんな症状ありませんか?
- 慢性的なかゆみ
- 食欲不振・体重低下
- 手足のむくみや顔のむくみがある
- 尿の色や匂いがいつもと違う
- 尿の泡立ちが多い
- 血尿が頻繁に出る
- 頻尿または排尿の回数が減る
- 降圧薬を服薬しても効果が見られない
当院の腎臓病治療体制

意外なほど身近なのが慢性腎疾患です。残存腎機能が60%以下の方が日本で、約2000万人おり、その中で慢性腎不全で透析治療に入る方が年3万人います。
当院は、蒲郡市と蒲郡市民病院、蒲郡市医師会が組織した「蒲郡肝臓病ネットワーク」に参画し、腎臓病診療向上を目指し、かかりつけ医と腎臓内科専門医と連携した治療にあたっています。
腎臓の役割
- 01
身体の老廃物を体外へ
尿として排出する。 - 02
体内の水分量の管理。
(むくみ、心不全の原因になります。) - 03
体内の塩分・カリウムなどの調節。
(むくみ、不整脈の原因になります。) - 04
体液の酸・アルカリの調節。
(PHの調節が悪いと体が
エラクなります。) - 05
骨髄に働き赤血球を
造らせるホルモンをだす。
(血液を造る。) - 06
骨代謝に関与しカルシウム・
リンの調節をする。
(骨が弱くなります。)
腎臓疾患の指標と対策
(医師も患者も)
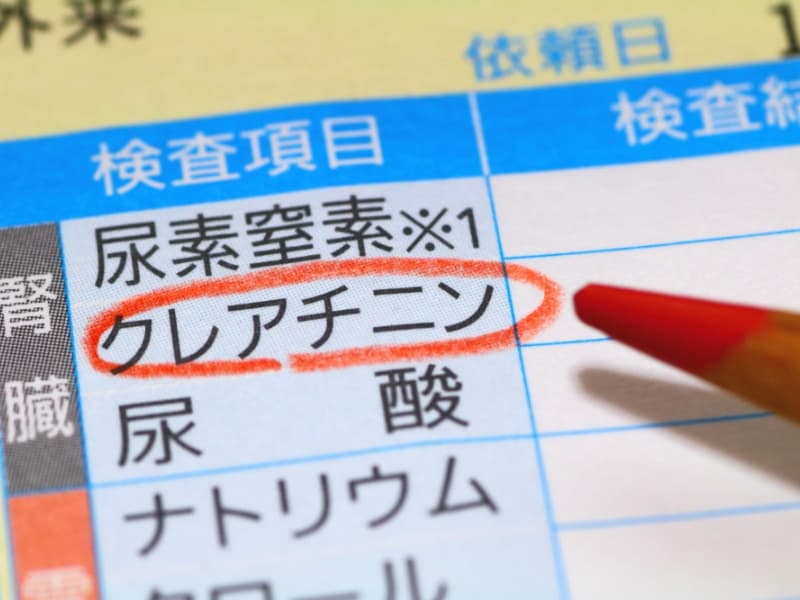
腎臓疾患は、検診で尿タンパクや潜血を指摘されたら、まず腎臓の異常か、又は尿管・膀胱・尿道の異常かをはっきりさせましょう。腎臓が血液の掃除をする残存能力(eGFR:糸球体ろ過率)がどれぐらいあるか調べてもらい又、知っておいてください。今はどの医療施設でも年齢、性別と血液中のクレアチニン濃度から直ぐ算出できるようになっています。
腎臓が血液の掃除をする残存能力(eGFR:糸球体ろ過率)
eGFR(糸球体ろ過率)が、残存腎機能の評価に世界共通で使用されます。
eGFR(糸球体ろ過率)は、60未満でより正確な値を示します。
eGFR(糸球体ろ過率)が52以下なら、もう腎臓内科受診が必要です。
 腎臓内科受診が必要な血清クレアチニン、尿蛋白の数値
腎臓内科受診が必要な血清クレアチニン、尿蛋白の数値
血清クレアチニンが、男性で1.0、女性で0.8以上なら注意。尿蛋白(2+)以上の場合、尿蛋白(1+)・尿潜血(1+)以上の場合も腎臓内科受診が必要です。
腎臓の予備能力/
残存腎機能

腎臓は再生能力のない臓器です。失われた腎機能は元に戻らないことが多いので気をつけましょう。腎臓は予備能力の範囲が大きいため、本来持つ機能の40%まで機能が低下しないと、血液検査で測る尿素窒素・クレアチニンの値が上昇して来ません。
検診でクレアチニン値が正常であっても、すでに50%以上機能が失われている場合もあるので注意が必要です。
 患者からの受診医の選択
患者からの受診医の選択
尿異常を軽視する医者や、血清クレアチニンが1.1(男性)、0.9(女性)以上でも見過ごしており、腎臓内科への紹介をしない医者はダメです。転医しましょう。多くの場合、腎臓内科に紹介される時には、残念ながら殆どの患者さんで既に腎機能が30~40%以下に低下してしまっている場合が多く、予後を大きく悪くしています。患者さんが疑問を持ち「残存腎機能:eGFR値」を聞いてください。殊更、糖尿病で通院中の患者さんには大事なことです。
腎臓疾患の治療

腎臓疾患は患者さん主導での治療を!
腎機能検査値が正常範囲でも、既に腎機能障害は始まっている可能性があり蛋白尿・血尿など尿異常を指摘されたら腎臓内科にご相談下さい。腎機能の低下が始まる前に機能低下を防ぐ対策が必要です。尿の蛋白が陽性か?クレアチニンの値はいくつか?医師に聞いて下さい。
患者さん側主導で、早期に腎臓内科受診を平行して行いまだ間に合う腎機能保護治療を受けるようにしましょう。将来透析治療を受けずに保存的治療のみで診ていける場合もあります。
- Flow01
減塩(6~7g/日以下)・たんぱく質制限(0.8~1g/kg)。
- Flow02
むくみがなければ、水分摂取を多く(尿量で1日2000ml目安。)摂る。
- Flow03
風邪・胃腸炎・疲労などの注意。過労働は避ける。
- Flow04
内服治療:原疾患により、異なりますので医師によく相談を・・・。
- Flow05
長い経過、治療になりますので焦らず、根気よく治療を続ける必要があります。
- Flow06
疾患によっては、ステロイドホルモン剤・免疫抑制剤・抗血小板剤・細動脈拡張剤・タンパク尿を抑える薬剤などを併用します。
- Flow07
原疾患の治療が優先される場合もあります。
腎機能障害が進んだ場合

腎機能障害が進むにつれて、以下の治療等が必要になります。
- 腎性貧血の治療:エリスロポエチン製剤投与。
- むくみの治療(腎・心機能、減塩に注意)。
- 血圧の管理(管理血圧を患者さんごとに設定必要)。
- 電解質の管理(高カリウム血症)。
- 体液酸性化の対策(血液の酸性度、塩素値に注意)。
- 骨代謝異常の管理(カルシウム/リン、Alp値に注意。)
腎臓疾患の管理は、患者さんの理解なくしては不可能です。
腎臓の検査
- 01
検尿・尿沈渣
- 02
血圧・脈
- 03
胸・腹部のレントゲン写真。心電図
- 04
血液検査。一般検査
腎機能の検査以外にも、風疹、糖尿病、リウマチ等の診断も行えます。 - 05
超音波検査(肝・腎・心臓・頚動脈など)
又は腹部CT。 - 06
腎炎の場合、確定診断として、経皮的腎生検査(総合病院へ紹介)など、疾患の鑑別により必要となります。
腎機能障害をおこす病気
- 風邪など感染症に伴う腎炎
- 慢性腎炎・子球体腎炎・リウマチ・膠原病
- 糖尿病・通風(高尿酸血症)・高脂血症
- 高血圧
- 循環器疾患(心不全・動脈硬化)
- 消化器疾患(肝臓疾患・胃腸障害・すい臓疾患など)
- 多発性のう胞腎、のう胞腎と腎炎の合併症
- 血液疾患
- 尿路感染症(反復)
- 薬剤障害
腎機能障害をおこす病気は上記等多彩な疾患に付随します。
-
急性腎炎
風邪の後にウイルスや細菌の影響で起こす腎臓の炎症です。
-
慢性腎炎
慢性腎炎の種類はたくさんあります。腎炎の種類により、また経過により治療法の選択が変わります。中には短期間に急激に悪くなり腎不全となる場合もありますが、活発な炎症があれば円柱がみられます。
-
腎障害
薬の副作用・先天的のう胞せい疾患・尿路感染症によりおこる腎機能障害などあります。腎不全に進行する事もあります。
-
急性腎不全症
著しい脱水状態、薬の副作用、尿路感染症や腎炎のなかで急に悪化する場合に急性腎機能不全に陥ることがあります。治療により戻る場合も多くあります。
-
慢性腎不全症
原因疾患では50%以上が糖尿病性腎症です。蒲郡市の場合はその割合がH19年には65%を超える勢いです。糖尿病の治療管理と「糖尿病性腎症の早期からの適切な治療管理が必要である」という意識が医師・患者ともに全国より低いということになります。
他、慢性腎炎・高血圧性腎硬化症・のう胞腎・膠原病性腎症・尿路感染症(慢性腎盂炎)・薬剤性などがあります。慢性腎不全は不可逆性の変化で元には戻りません。現在残る腎臓機能をいかに守り維持していくかが大切な治療です。